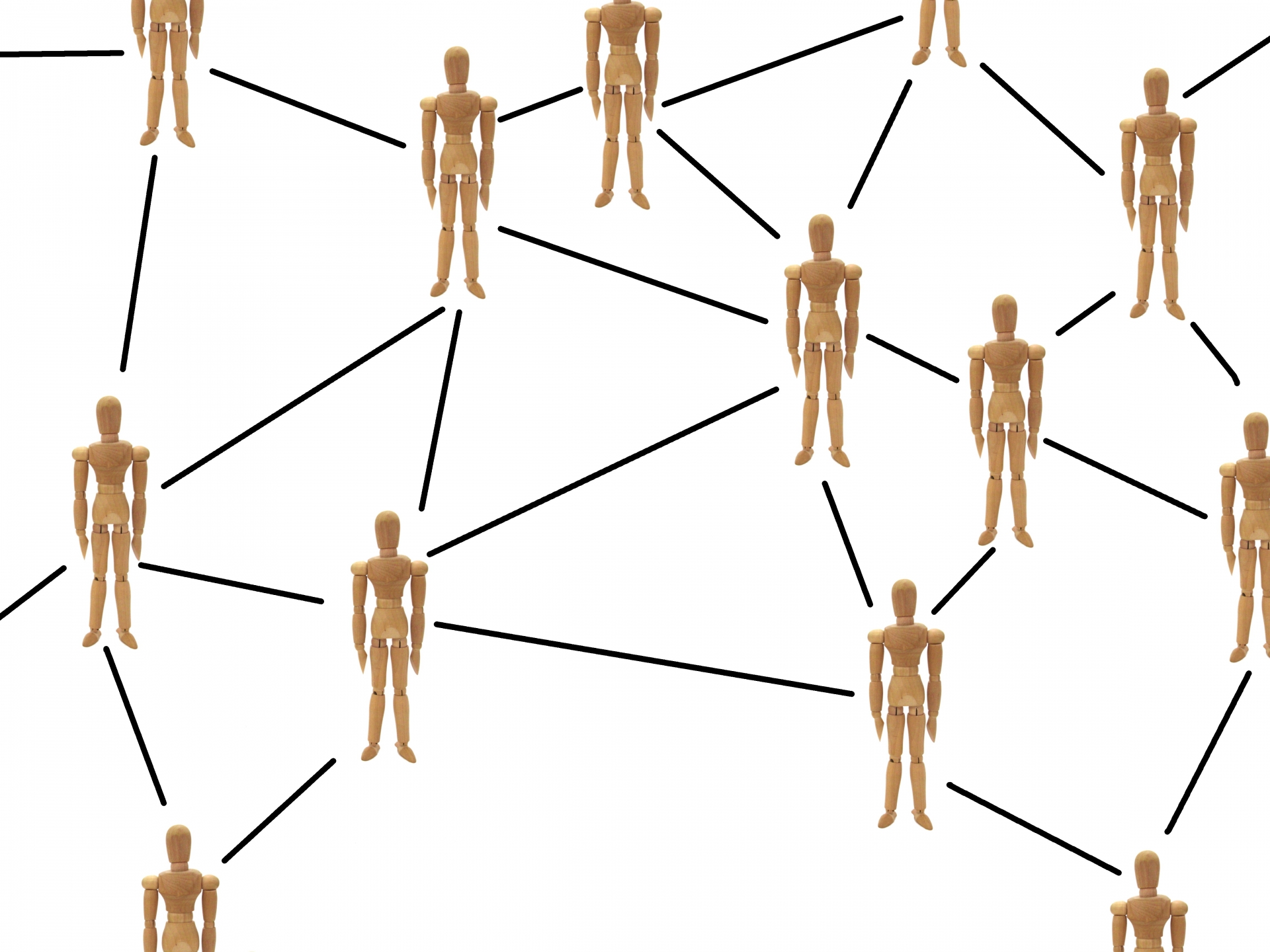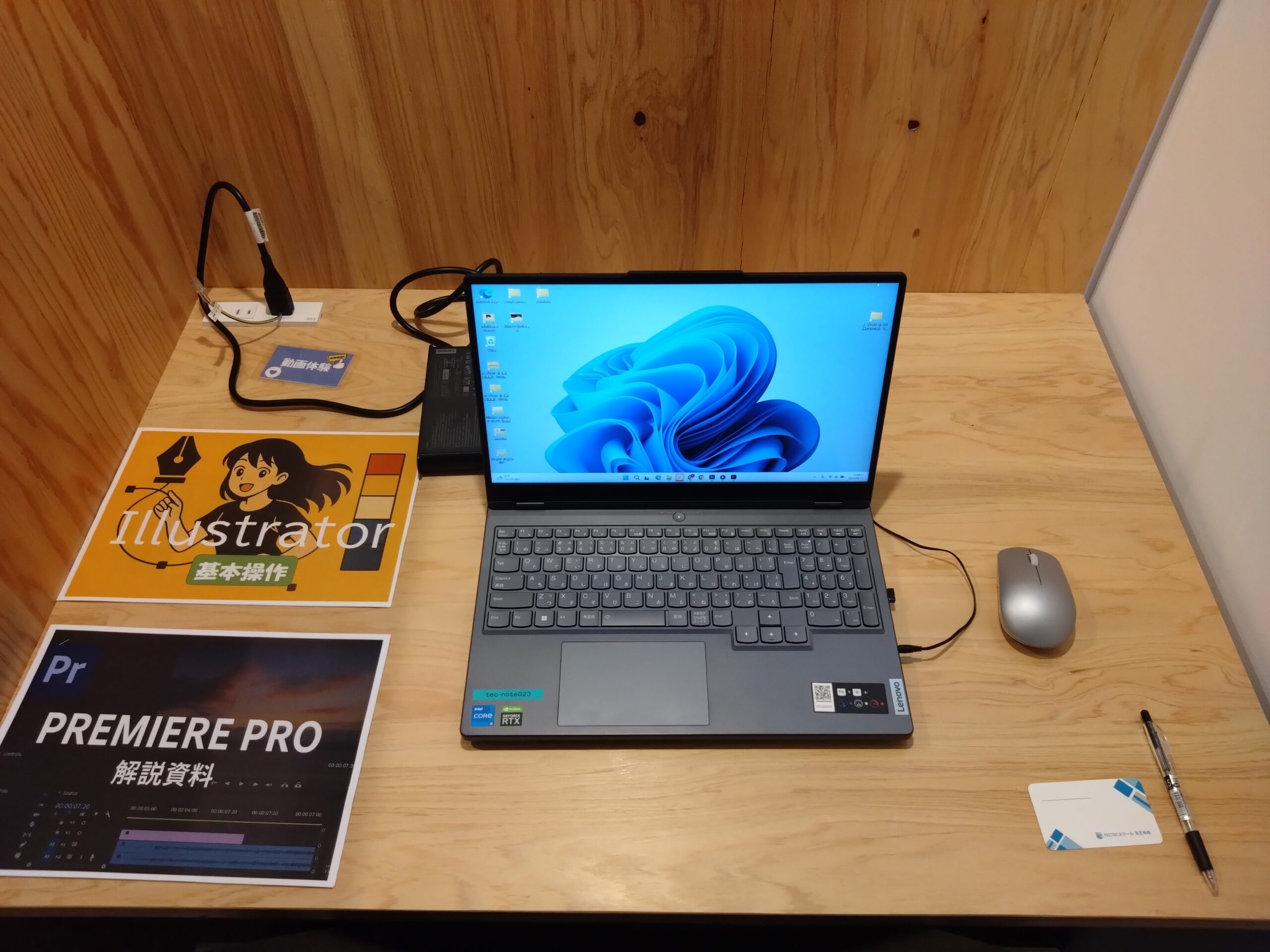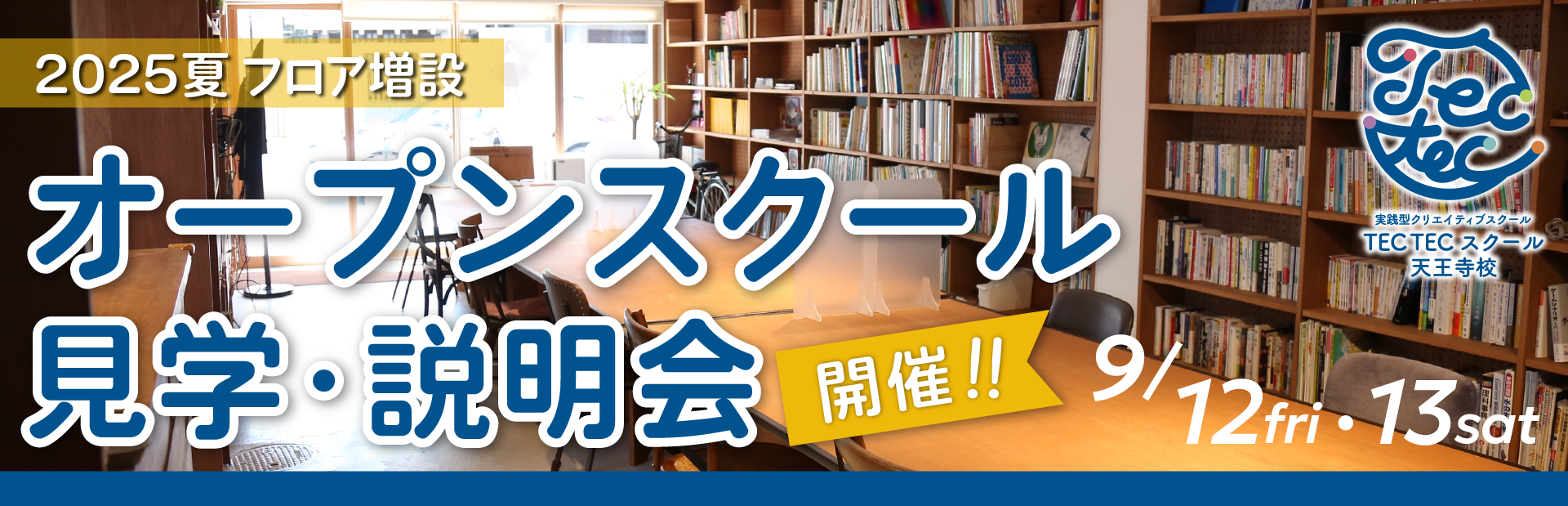TECTEC中田です!
発達障害児童の数が年々増加傾向にあるといわれています。
2019年の文部科学省調査によると、軽度の障害やグレーゾーンの子どもが指導を受けるための「通級指導教室」に通っている国公私立小学校、中学校及び高等学校の児童生徒数は13万4185人とのことです。
1993年のデータを見ると、高校生がカウントされていないものの小・中学生だけで1万2259人となっており、単純に約11倍増加していることになります。
また、こちらも2022年の文部科学省調査によると、通級指導教室ではなく通常学級に通っている小・中学生のうち8.8%(約12名に1名)に「学習や行動に困難のある発達障害の可能性がある」ことが認められる結果となりました。
これは公立の小中学生と高校生約8万8500人を抽出し、学習や対人関係で困難を抱える子どもの数を集計した際のデータで判明したものであり、全国の公立小中学校で推計すると「70万人超」に発達障害の可能性があるとされています。

少子化が進み、児童数が減っているにもかかわらず、発達障害児童が増えている傾向は以前から問題視されていました。
ですが、これは決してマイナスの要因ばかりではありません。
近年では小児科学・児童精神科学の分野において「発達障害の診断基準」が変更され、それまでは障害とみなされなかった軽度の発達障害も支援の対象となり、適切なサポートを受けられるようになりました。
支援の手が届かなかった子どもにも診断名がつくことで、精神医療の領域からアプローチできるようになったというのは大きな進歩ではないでしょうか。
また「障害に対する理解」が広まり、保護者が児童とともに精神科医に訪れることや、発達障害の診断が下されることに対する抵抗感が以前よりも薄れているというのも大きく影響しています。
発達障害は「第4の障害」として2000年以降に既存の「身体・知的・精神」の3障害の支援制度に組み込まれ、さらに2010年に障害者自立支援法が改定されたことにより、発達障害の人も精神障害者保健福祉手帳を取得することができるようになりました。
つまり、発達障害の方に対する公的な福祉面でのサポート自体が、15年以上前には存在しなかったのです。
発達障害という言葉やその症状に関しても、ここ数年間で急激に認知度が上がり、発達障害であることをカミングアウトしやすい社会の雰囲気が醸成されています。
病院にだけ何年も通い続けて何も解決策がなかった時代よりは、発達障害と診断された事実を周囲に伝えることでむしろ「生きづらさを軽減するためのアドバイスを受けやすくなった」といえるでしょう。

一方で、発達障害が増えたのを「医学の発達」「多様性を認める社会になった」と楽観的に考えてばかりいてもいけません。
発達障害は「生まれつき」と考える人が多く、実際「遺伝的に発達障害の素質を持った子ども」は一定割合存在しています。
ですが、日常生活において発達障害の傾向が顕著に現れるかどうかは、環境的な要因も関係してくるというのが最新の研究で唱えられているようです。
今は小学校低学年からスマホでSNSを閲覧したりゲームで遊んだりするのが珍しくありませんが、ネットから得る情報量が多すぎるという外的なストレスや、スマホに夢中になることによる睡眠不足などは「発達障害の傾向をより強める」とされています。
また、発達障害特有の問題行動を起こしてしまった際に、周囲の理解がなく過度に叱責されるといった精神的負担が二次障害を引き起こすことも。
ただし、このあたりの因果関係に関しては専門家の間でも意見の分かれるところですので、今後さらに研究が進んでいくものと思われます。
いずれにせよ、子どもにとって大切なのは「一人ひとりが伸び伸びと成長できる環境」を大人達が用意することです。
発達障害の診断を受けて手帳を取得したとしても「手帳の恩恵以上に周りの人間が支えてくれる」社会こそが真のインクルーシブな社会であるといえるでしょう。
※本文中のデータ・最新情報などは以下のサイトを参考にさせていただきました。
<発達障害・精神疾患支援チャンネル>
【最新統計】通級に通う発達障害児(自閉症・ADHD・学習障害)の人数
<日本経済新聞>
<すらら>
【知的障がい者が増加している4つの原因】障がい者人口の推移や知的障がいの診断基準についても解説
<Kaien>
発達障害のグレーゾーンの方は障害者手帳をもらえない?取得の方法や支援を受けるコツを詳しく解説
<BRAIN CLINIC>